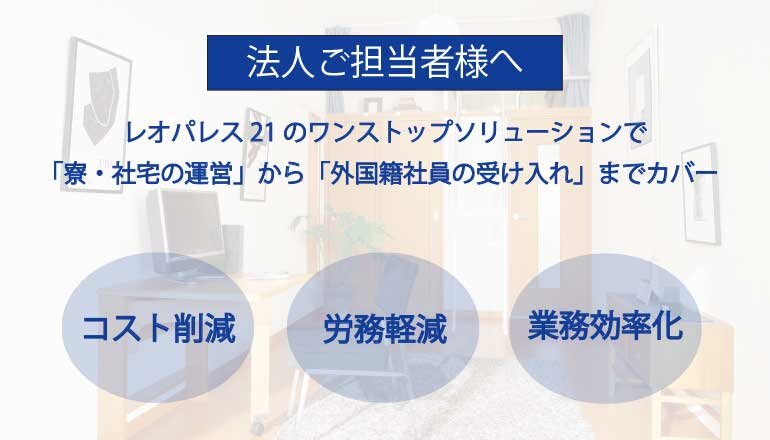企業文化の変革は
不断の努力
施工不備とガバナンス
レオパレス21は過去数年間、ガバナンスの向上やコンプライアンスの徹底に取り組んできました。
私が社外取締役に就任した2020年当時、取締役会は創業者経営時代の影響を残しており、本気でガバナンスと向き合っているとは感じられませんでした。オーナー様から請け負った仕事を責任もって完遂し、入居者様に快適で居心地のよい住戸を提供するという基本をないがしろにしていなければ、施工不備問題は起こり得ないはずです。
要するに、会社の上層部ばかりを見るという体質が原因と考えられます。ここでいうガバナンスとは、株式会社が株主の利益にかなう形で公正に経営されているかを監視する「コーポレート・ガバナンス(企業統治)」という仕組みを指しています。会社というものはよい仕組みがなければ容易に逸脱が起こります。当社の施工不備問題も、まさにガバナンスが機能しなかったことに起因していました。
そこを変えずに変革は進みません。本来、社外取締役は、経営資源の活用の妥当性を監視する役割を担うものですが、旧態依然とした取締役会に危機感を抱いた私は、どのようにガバナンスを高めていくかという執行の領域にも踏み込んだ意見を述べるようになりました。一歩ずつ前進していますが、まだ十分とは言えません。企業文化の変革には長い時間がかかります。努力し、日々の行いを顧みることなくして、よい習慣は身につきません。トップも自分自身を変えなければいけないし、会社も単に制度を改めるだけでなく、持続的に実践していくことが求められるのです。
持続的な実践にあたっては、言葉の本質を理解しないまま上滑りの議論をするようなことは避けなければなりません。情報や制度というものはすべて、物事の原点に立脚した上で整理していくべきであり、このガバナンスという仕組み本来の意味を理解するには、株式会社の原点に立ち返る必要があります。
東インド会社
株式会社の原点は1602年にオランダに生まれた東インド会社です。17世紀初頭に国力を飛躍的に発展させたオランダでは、一時は東インド貿易関連の会社が数十社乱立しましたが、後から参入してきたイギリス、フランスに対抗するため、国内の東インド貿易関連会社の統合を図ります。そこで採られたのが、金を出す者、船を提供する者や船長・船員の分業体制であり、各自の出資割合などに応じて利益を配分する株式の仕組みも発明されました。しかし、初期には利益配分において不正が多発し、船員の暴動なども発生したため、組織を監視・統制するスキームの必要性が認識され、今日のコーポレート・ガバナンスにつながる仕組みができたのです。つまり、株式会社は「資本の塊」であるため、ガバナンスがなければ重大な不正が起きかねないものであり、不正を監視する仕組みも株式会社の原点の時代から存在していたのです。
ガバナンスは幸福の追求
もう一つ、株主が投資をする理由からも、ガバナンスの本質を理解できます。投資するのは値上がりや高利回りの配当を期待するからであり、値上がりを期待する理由は、儲けて豊かになりたいからです。ではなぜ豊かさを求めるのかというと、それはつまるところ、家族がハッピーになるためです。家族の幸せのための投資なら、株主にとっては、一過性の利益より中長期にわたって配当がある方が望ましく、会社は中長期的に存在が許され続けるものである必要があるわけです。当然コンプライアンス(法令遵守)は最優先事項となりますし、周囲の人に「よい人」「よい会社」と思ってもらえることも重要になります。不正を監視し、株主の利益を最大化する仕組みである「ガバナンス」を噛み砕くと、このようになります。実は、日本の株式会社法には「ガバナンス」という言葉も「コンプライアンス」という言葉も存在しません。当社に限らず、日本ではこれらの本質的な理解が抜け落ちたまま議論されてきたのです。日本で「ガバナンス」という言葉が広く知られるようになったきっかけの一つは、一橋大学名誉教授の竹内弘高氏による日本のバブル崩壊についての発言だったと記憶していますが、ハーバード大学ビジネススクールで教鞭をとっていた竹内氏の紹介したガバナンスは、株主利益の最大化を求める、いわばアメリカのガバナンスでした。もちろん株主利益の最大化は間違いではありません。しかし、1979年に西洋史学者の故・木村尚三郎氏が『和魂和才のすすめ』を書き、西洋の技術を大和心で活用することが日本にとって重要だと説いたように、また、渋沢栄一が『論語と算盤』(1916年)で道徳や公益性を重んじたように、当社も上滑りの議論で満足することなく、精神性や倫理観も踏まえた議論を進めてほしいと思っています。社会からの信頼回復の鍵も、そのようなところにあるはずです。
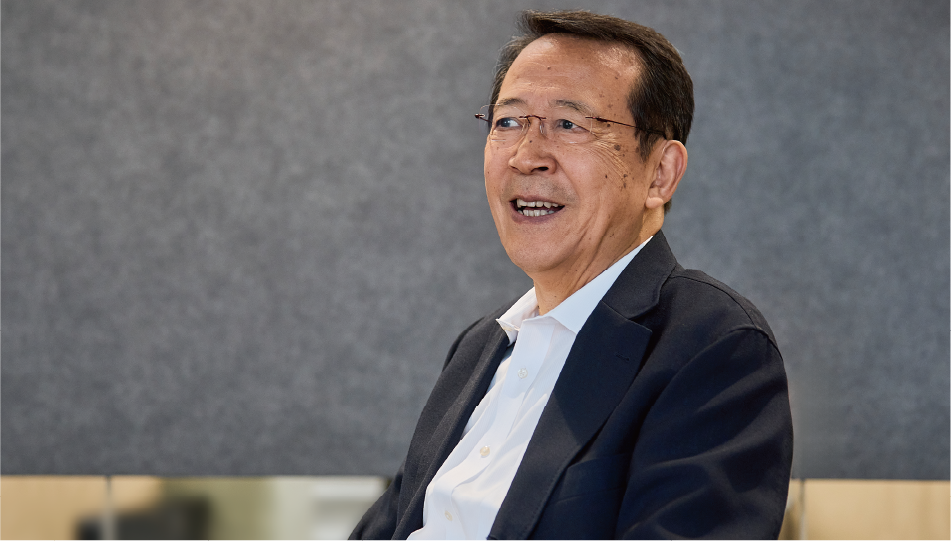
ガバナンスは働く誇り
ガバナンスは人生そのもの
コーポレート・ガバナンスは、実は従業員自身の生活、人生にも直列的に関連しています。現代の株主の多くが銀行や証券会社などの機関投資家ですが、そのうち最大の機関投資家は年金基金です。つまり、資金の出どころは、実は皆さん一人ひとりを含めた社会全体なのです。年金基金が運用益を得なければ、従業員の将来の生活にも影響が出ます。大学や研究所も、寄付された基金などを、より研究・教育活動に活用できるよう投資をしています。そう考えると、ガバナンス=株主利益の最大化は、自分自身にも、また、社会のあらゆる人にも直結する問題であると理解できるはずです。ガバナンスは人生そのものなのです。
当事者意識こそが会社のガバナンスを支える根幹です。当社では「社員が主役」を目指した社内風土改革が進んでいるものの、私が見るところ、まだまだ当事者意識が十分とは言えません。当事者意識とは、自分自身のこととして考え、目的を達せられるよう行動し、結果に責任を持つということでもあります。例えば、中長期計画などで右肩上がりの成長を掲げることは簡単ですが、むしろガバナンスの本質を顧みたときに重要となるのは、計画が下振れしそうなときにどう対応して克服するのかという視点であり、それを実際に実行することです。エリア支社制度を導入し、権限を各エリアに委譲する体制も準備が進みつつありますが、制度をつくっただけでは成果は上がりません。実行力と、検証力と、それを支える指導力が必要となることを忘れてはなりません。
働く誇り
そうした自律的な行動を促すには、人材育成が重要です。人材育成に即効性はありませんが、徐々に効果は上がり始めているように思います。しかし、過去に大きな不祥事を起こした会社が優秀な人材を集めるのは簡単ではありません。だからこそ、社員がこの会社で働くことに誇りを感じられるような環境づくりが必要となります。
私はその一環として、当社の経営資源である単身者用住居を活用した奨学制度を提案しました。2025年4月のスタート以来、社内外から大きな反響があったと聞いています。自社に公益性の高い制度があることは、自己の存在意義の確認につながり、自己肯定感を高めます。今後はスポーツ、吹奏楽、俳句などの社内サークルの設置も提案するつもりです。共通の目標を持つことで連帯感を育み、祭りのような場を通して帰属意識や人への敬意、多様性への理解を育んでいく。そのようなこともまた、ガバナンスを高める企業文化へとつながると考えています。
信頼回復−終わりなき改革
マイナスからのスタート
施工不備問題に一定の決着がついたとはいえ、当社の再スタートはゼロからではなく、マイナスからの出発です。当たり前のことを当たり前にするだけでは、失った信頼の回復には至りません。浮かれることなく、どのように信頼を取り戻していくのか、真剣に考え、行動していただきたいと思います。
改革には終わりがなく、不断の努力が求められます。従業員の皆さんが日々の仕事を通じてガバナンス改革を実践していくためには、人間や社会についての横並びの発想をやめ、深く洞察することも大切です。ぜひスマホから少し離れて本に親しみ、特に古典を通じて、人間という存在について考えていただきたいと思います。
世のため人のため
そもそも人間が生きるということは、世のため人のためにならなければいけないということです。社会が分業化しているのは、それぞれが得意な仕事を担うことで、社会全体の幸せの総量を増やすためです。つまり、社会に役立たない会社は存在が許されないのです。自分の専門性が誰かの幸せにつながっていると認識して、日々の仕事に向き合わなければ許されないのです。
そして、私がここで述べたことを一過性のものとして流さず、しっかりと受け止め、考え、行動につなげてください。もし上司に問題提起をしたとしても、期待通りの返事はないかもしれません。それでも、一人ひとりの行動が会社を変え、ガバナンスを育むのだと信じて、挑み続けていくしか選択肢はないのだと覚悟を決めてくれることを期待しています。

外部からの評価
-
- 各評価サイトへ移動します。
SERVICE SITES サービスサイト
- 各サービスサイトへ移動します。